2025年9月22日更新
- 本文や見出しを一部修正・変更しました。
- その他各種修正
2025年7月31日更新
- 「はじめに」の部分に「この記事をぜひ読んで欲しい人」の記載を追加
- 記事末尾に当記事の続編記事へのリンクを追加
- 「タグ」の追加
- その他本文を一部修正
はじめに
当記事の要約
- 精神障害(精神疾患・こころの病気)や発達障害(神経発達症)を持ちながら精神保健福祉士を目指す人には、健常者にはない難しさがいくつも存在すると思われる。
- 学校選びの段階では、学校側の「合理的配慮」やその他学習支援についてよく吟味しなければならない。それと入学後は体調管理や学習意欲の維持に苦労する可能性が高い。
- 実習を受ける人は、あらかじめ学校や実習先とよく相談し理解を得る必要がある。心身の負担に考慮した実習計画の策定や、自らの病気・障害を事前に十分理解することで、無事実習を終わらせたい。
- 精神保健福祉士国家試験の対策や実際の受験は、心理的ストレスが大きい。工夫しながら乗り切りたい。
この記事をぜひ読んで欲しい人
精神保健福祉士を目指す精神障害者・発達障害者はときどきいる
主に精神保健医療福祉分野で働く福祉専門職「精神保健福祉士」(MHSW・PSW)は、主に統合失調症や双極症(双極性障害)・うつ病といった精神疾患・精神障害を持つ方を支援する。
それと近年急速に認知度が高まったASD(自閉スペクトラム症)・ADHD(注意欠如・多動症)などの発達障害(神経発達症)を持つ方を支援する精神保健福祉士も多い。
最近私の周りでこの精神保健福祉士になろうとする精神障害や発達障害の当事者が少しずつ増えてきた。実際私の知人の当事者で精神保健福祉士になった人がいる。またこの資格の取得を目指し学校で勉強している人もいる。
当ブログの筆者はうつ病と発達障害と言われたことがあるものの、無事に精神保健福祉士(と社会福祉士)の資格を取った経験がある。
そこでこのブログ記事では、精神保健福祉士を目指す精神障害者や発達障害者が資格取得前に直面しうる難しさについて、私見を具体的に述べる。精神保健福祉士の国家資格取得を検討する精神障害や発達障害の当事者の参考になれば幸いである。
当記事は、2024年4月に投稿した次の2記事を現状に合わせて書き直したものの1つである。

【前編】発達障害者・精神障害者の精神保健福祉士国家資格の取得→取得前後の難しさ
発達障害者や精神障害者が精神保健福祉士の国家資格を取得する際に事前に考えておかないといけないことについて述べる。前編は資格取得前後にある難しさについて書いている。

【後編】発達障害者・精神障害者の精神保健福祉士国家資格の取得-取得を検討できる場合とまとめ
発達障害者や精神障害者が精神保健福祉士の国家資格取得を検討できるケースや、資格取得後に場合によっては働くことの困難さがあること、それと話のまとめ。
今後別の記事で
- 精神保健福祉士になった後に待ち受ける壁→公開済み
- 精神保健福祉士の資格取得を検討して良い場合
などを改めて取り上げたいと思う。
当記事の構成
2~3ページ目:精神保健福祉士になるまでにいくつもある難しさ
精神障害者・発達障害者が、精神保健福祉士の国家資格を取得するまでにある複数の困難さについて、それぞれ具体的に説明する。
4ページ目:当記事のまとめ
短いものの当ブログ記事をまとめた。私個人が本気で精神保健福祉士を目指す精神障害者・発達障害者に伝えたいメッセージもある。
リンク


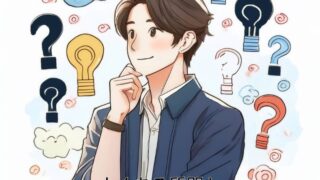








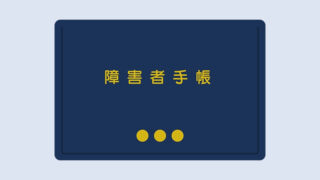

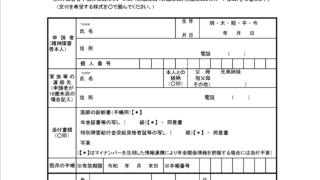









コメント