2025年3月4日更新
- 見出しや本文の一部を追記・修正しました。
- 「あわせて読みたい」のブログ記事リンクを追加しました。
2025年2月6日更新
- 「タグ」「カテゴリー」を追加しました。
- より読みやすくなるように見出しや本文の一部を追記・修正しました。
- 「前編のおさらい」部分の一部リスト表示の追加
- 記事中・記事末尾のブログ記事のリンクを追加しました。
2024年7月19日更新
- タイトルを更新しました。
- 旧タイトル:「【後編】発達障がい者・精神障がい者が精神保健福祉士の国家資格を取得することについて」
- より読みやすくなるように表現の一部を修正しました。
- 見出しや本文を追加・修正しました。
- 最初に「前編のおさらい」「後編の記事の要約」「後編記事の構成」を追加
- 段落やページ構成の変更
- 「まとめ」内のTipsの記載について、現状に沿った内容に修正
- 参考になるブログ記事のリンクを掲載しました。
はじめに
前編のおさらい
この記事は前編・後編の後編です。先に前編をご覧ください。
- 発達障害や精神障害・精神疾患の当事者が精神保健福祉士の国家資格を取得しようとする場合、取得するまでの学習の段階、取得後に資格を活用する段階のどちらにも難しさがある。
- 精神保健福祉士の資格取得までの学習の段階では、次の3つが発達障害や精神障害・精神疾患の当事者にとって高いハードルになると思われる。
- 「日々の勉強」
- 「2回ある実習」
- 「国家試験」
- 発達障害や精神障害・精神疾患を持つ人にとって、精神保健福祉士の資格取得後は、以下の3つが難しい課題になりそうである。
- 「意思疎通」
- 「自らの障害の捉え方」
- 「自分自身のメンタルヘルスケア」
後編記事の要旨
- 発達障害や精神障害・精神疾患の当事者が精神保健福祉士の資格取得を検討できるのは、「ピア精神保健福祉士」を目指す場合や、精神保健医療福祉に強い興味があり学びたい場合である。
- 現実的な問題として、精神保健福祉士の資格を取得しても、発達障害や精神障害・精神疾患ゆえにこの資格を活かして働くことが困難な状態に直面するかもしれない。
- 発達障害や精神障害・精神疾患当事者の精神保健福祉士は、同じ精神障害者・発達障害者にとって、社会をより良い方向に変えうる。
後編記事の構成
次の2ページ目では、前編の内容を踏まえて、発達障害や精神障害・精神疾患の当事者が精神保健福祉士の国家資格の取得を検討できる場合についての私見を具体的に述べる。
3ページ目では、発達障害者や精神障害者が精神保健福祉士の資格を取得しようとする場合にあらかじめ理解しておきたいことについて書く。
最後の4ページ目はまとめである。経験者として私自身のメッセージも少し盛り込んだ。
リンク

のスクリーンショット-320x180.jpg)











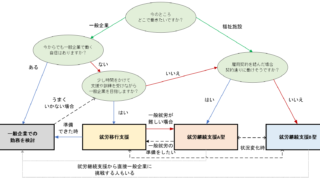



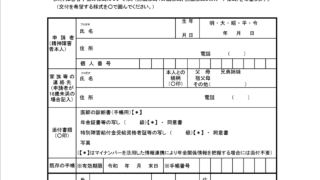





コメント