2025年7月2日更新
- ページ数を増やしました。
- ページ区切りの位置も調整しました。
- 見出し・本文の一部を追記・修正しました。
- 記事冒頭に「自己紹介」の内部リンクを追加しました。
- 「タグ」を追加しました。
2025年2月25日更新
- よりシンプルに読みやすくするために本文を追記・修正しました。
- 文字修飾の一部変更
- 広告を貼り替えました。
- 「タグ」をさらに追加しました。
過去の更新情報
2025年2月4日更新
- 「カテゴリー」「タグ」を追加しました。
- より読みやすくなるように本文と見出しを一部追記・修正しました。
- 「当記事の要旨」の場所の変更
- 末尾の「あわせて読みたい」のブログ記事リンクを追加しました。
2024年7月19日更新
- タイトルを更新しました。
- 旧タイトル:「【前編】発達障がい者・精神障がい者が精神保健福祉士の国家資格を取得することについて」
- より読みやすくなるように表現の一部を修正しました。
- 見出しの修正・追加
- 最後に「前編のまとめ」を追加しました。
- 参考になるWebサイトのリンクを追加しました。
- その他修正
- 記事の「抜粋」の修正・追記
この記事は前編・後編に分かれています。当記事は前編です。
後編もぜひあわせてご覧下さい。
はじめに
当記事の要旨
- 発達障害(神経発達症)や精神疾患・精神障害の当事者が精神保健福祉士の国家資格を取得する場合、資格取得までの段階で障害ゆえの難しさに直面する可能性が高い。
- 資格取得後も精神保健福祉士としての活動が困難になるリスクも事前に考慮しないといけない。
当記事について
私はもともと「広汎性発達障害」(神経発達症・ASDとADHD両方の要素がある)があり、この発達障害の影響で受けたいじめにより「うつ病」になった経験がある。
その私はアルバイトで働いたりピアサポート活動をしたりしながら大学の通信教育を受けて、何とか精神保健福祉士(と社会福祉士)の資格を取得した。
ひょっとしたら、私と同様に発達障害や精神障害・精神疾患を持つ人で、精神保健福祉士の国家資格の取得を検討している人もいるかもしれない。
だが私は正直に言って、そう簡単にこの精神保健福祉士の国家資格の取得を勧めることはしない。この記事ではまずその理由について述べる。もちろん精神保健福祉士の資格の取得を検討しても良い場合もいくつかあると考えている。後編記事でそのことについても触れる。
リンク








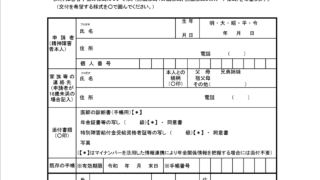







のスクリーンショット-320x180.jpg)
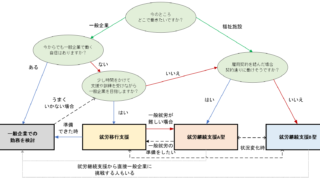





コメント