この記事は、過去に投稿した以下の2つの記事のフルリニューアル版です。
はじめに
記事を読む前に…
精神障害(精神疾患・こころの病気)や発達障害(神経発達症)を抱えながら、次のように考えたことはないだろうか。
- 「精神保健福祉士の資格を取りたいけれど、本当に自分に必要なのだろうか」
- 「精神保健福祉士になった後、資格を活かして十分に活動できるのか」
私自身も、かつて同じように迷った経験がある。
精神保健福祉士(MHSW・PSW)の資格取得には、学習や実習などの大きな負担が伴い、仕事や生活との両立は決して容易ではない。だからこそ、安易に決断できるものではなかった。
一方で、この資格を持つことで活動の幅が広がり、支援者としての信頼性が高まる可能性があることも実感した。
その経験から、精神障害や発達障害の当事者がこの資格の取得を検討する際には、
「どのような条件に当てはまる人が前向きに考えて良いのか」
を整理しておくことが重要だと考えるようになった。
本記事では、精神障害や発達障害の当事者が精神保健福祉士の資格取得を積極的に検討できる条件を3つに整理し、経験者としての私見を交えながら、判断の手がかりを提示する。
この記事の要約
- 精神障害や発達障害の当事者が精神保健福祉士の資格取得を前向きに検討できる条件は、次の3つである。
- 「ピア精神保健福祉士」として活動したい場合
- 精神保健医療福祉に強い関心を持ち、体系的に学びたい場合
- すでに医療・福祉分野で働いていて、業務の幅を広げたい場合
- これらはいずれも、資格取得が「自らの経験や関心を活かし、次のステップに進むための手段」となり得る。
- 一方で、資格取得には学習や実習などの負担が伴い、仕事や生活との両立が課題になることもある。
この記事をぜひ読んで欲しい人
この記事のこの後の流れ
2ページ目:精神保健福祉士の国家資格取得を前向きに検討できる場合
精神障害や発達障害を持つ人が、精神保健福祉士資格の取得を積極的に考えて良い場合を3つ提示する。それぞれについて、背景・メリット・注意点を整理し、筆者自身の経験を交えて説明する。
3ページ目:まとめ
これまでの内容を振り返り、3つの条件を再度整理する。あわせて、資格取得を検討する当事者に向けて、経験者としての筆者からのメッセージをお伝えする。
リンク
リンク












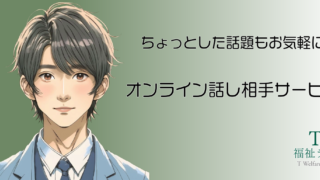
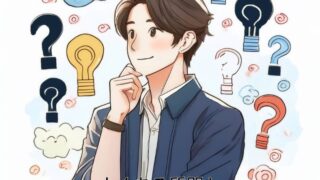

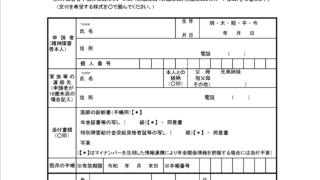

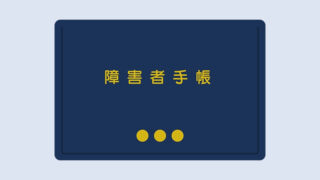

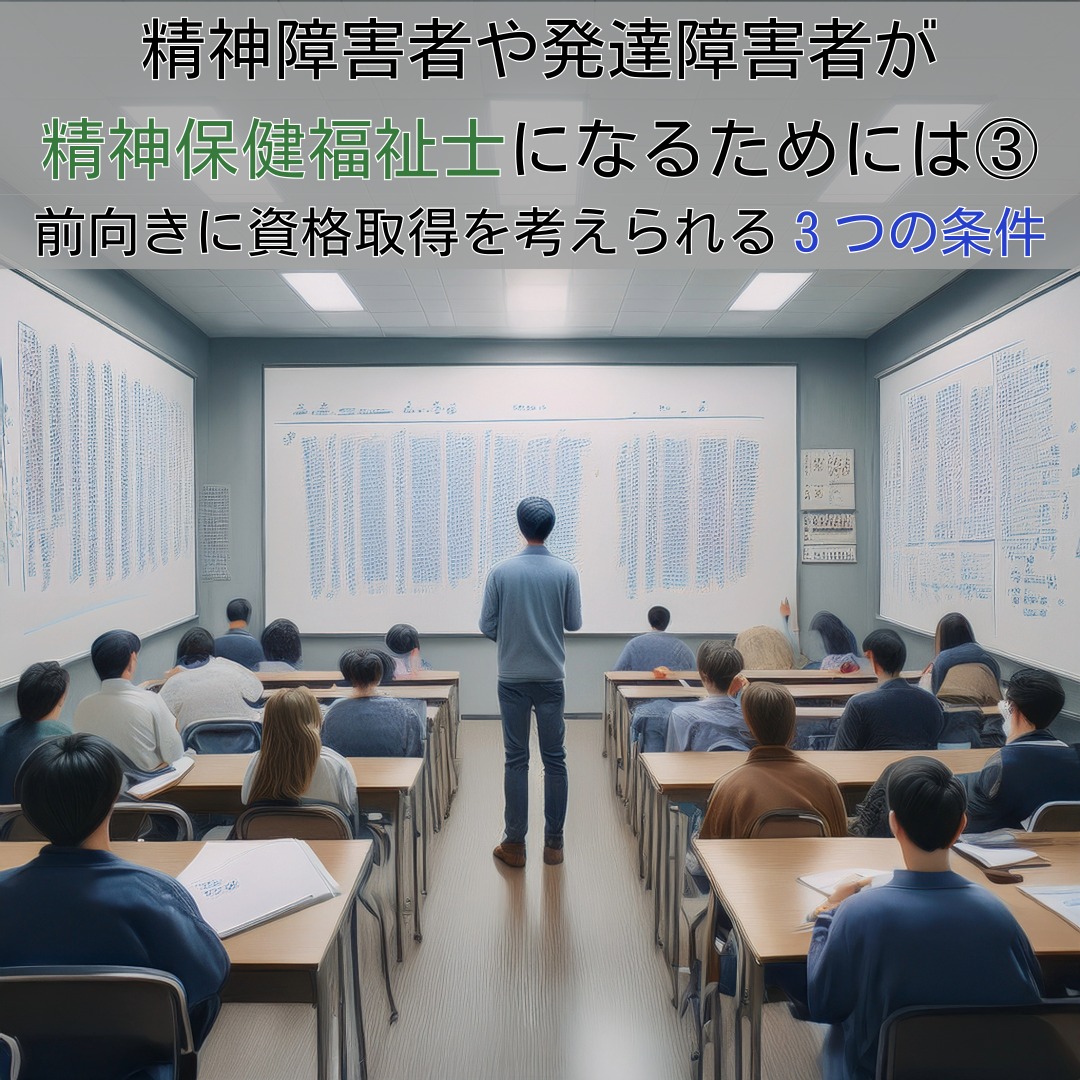




コメント