精神保健福祉士の国家資格取得を前向きに検討できる場合
精神障害や発達障害の当事者が精神保健福祉士の国家資格取得を前向きに検討できるのは、以下の3つの場合である。
- 「ピア精神保健福祉士」として活動したい場合
- 精神保健医療福祉に強い興味関心があり、しっかり学びたい場合
- すでに福祉・医療分野で働いていて、業務の幅を広げたい場合
①「ピア精神保健福祉士」として活動したい場合
現在、ピアサポーターとして活動する当事者が「ピア精神保健福祉士」として活動するためには、精神保健福祉士の国家資格が不可欠である。
ピアサポーターは、専門職である精神保健福祉士と連携して支援に当たる場面が少なくない。
ピア精神保健福祉士は、ピアサポーターとしての当事者視点と、精神保健福祉士としての専門的視点の両方を理解し、活かすことができる。
そのため、両者の間をつなぐ橋渡し役として機能し、支援の質や幅を広げる存在となり得る。
自らの病気・障害に関する経験を活かしつつ、ピアサポートの理念を大切にしながら、当事者を専門的に支援したいと考える人にとって、ピア精神保健福祉士は有力な選択肢である。資格を得ることで活動範囲が広がり、支援者としての信頼性も高まる大きなメリットもある。
②精神保健医療福祉に強い興味関心があり、しっかり学びたい場合
多くの精神障害者や発達障害者は、次のような精神保健医療福祉制度・サービスを利用しながら生活している。
- 精神障害者保健福祉手帳の取得
- 就労移行支援事業や就労継続支援事業(A型・B型)の利用
- 各種相談支援事業所や発達障害者支援センターでの相談
また当事者として社会生活を送る中で、次のような特有の経験をすることもある。
- さまざまな「生きづらさ」を感じる(人間関係や仕事など)
- 障害による差別や偏見を受ける
こうした制度・サービスの活用や当事者としての経験が、精神保健医療福祉への関心を高めるきっかけになる場合がある。さらに、私のようにこの分野を研究したいと考える人も少なからずいるだろう。
もしこの分野に強い興味を持ち、体系的に学びたい場合は、その過程で精神保健福祉士の資格取得を検討する価値がある。
保健福祉系大学や専門学校の精神保健福祉士資格課程では、精神保健医療福祉に関わる制度・サービス、精神障害者や発達障害者が直面する社会問題について幅広く学ぶ。さらに、医療職と協働するために必要な精神疾患や治療に関する基礎知識も習得する。
こうして得た知識を、卒業後や資格取得後に活かせる場があるなら、学びと資格取得の両方に取り組むことは大きな意義があると言える。
③すでに福祉・医療分野で働いていて、業務の幅を広げたい場合
精神障害や発達障害を抱えながら、福祉や医療の現場で働く当事者も少なくない。
例えば、病院の看護助手として勤務したり、福祉事業所で支援員として活躍したりするケースがある。すでに同じ障害を持つ人を援助している場合もあるだろう。
このような人が、もし時間や体力に余裕を持てるなら、精神保健福祉士の資格取得を検討する価値がある。資格を得ることで、業務の幅や役割を広がり、賃金や待遇が改善される可能性もある。
具体的には、次のような場面が考えられる。
- 精神科医療機関:精神科ソーシャルワーカーとして、各種専門業務を担えるようになる
- 福祉事業所:資格手当が付与され、サービス利用計画の作成などの専門的な業務に携われる
資格を持つことで、現場での発言力や信頼性が高まり、より専門性の高い役割を担える可能性が広がる。さらに、当事者としての経験を活かすことで、支援に独自の視点を加えられることも大きな強みである。チームの中での存在感も増すだろう。

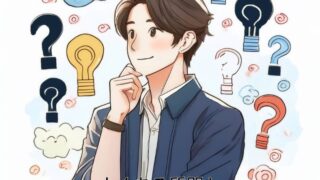
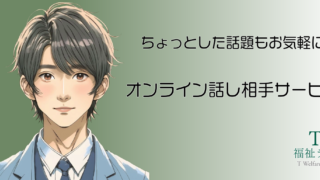


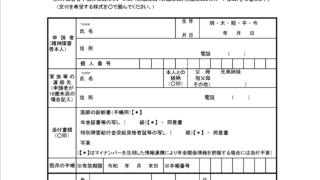









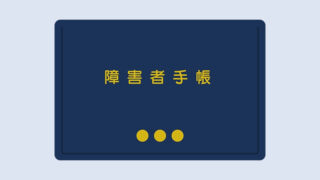



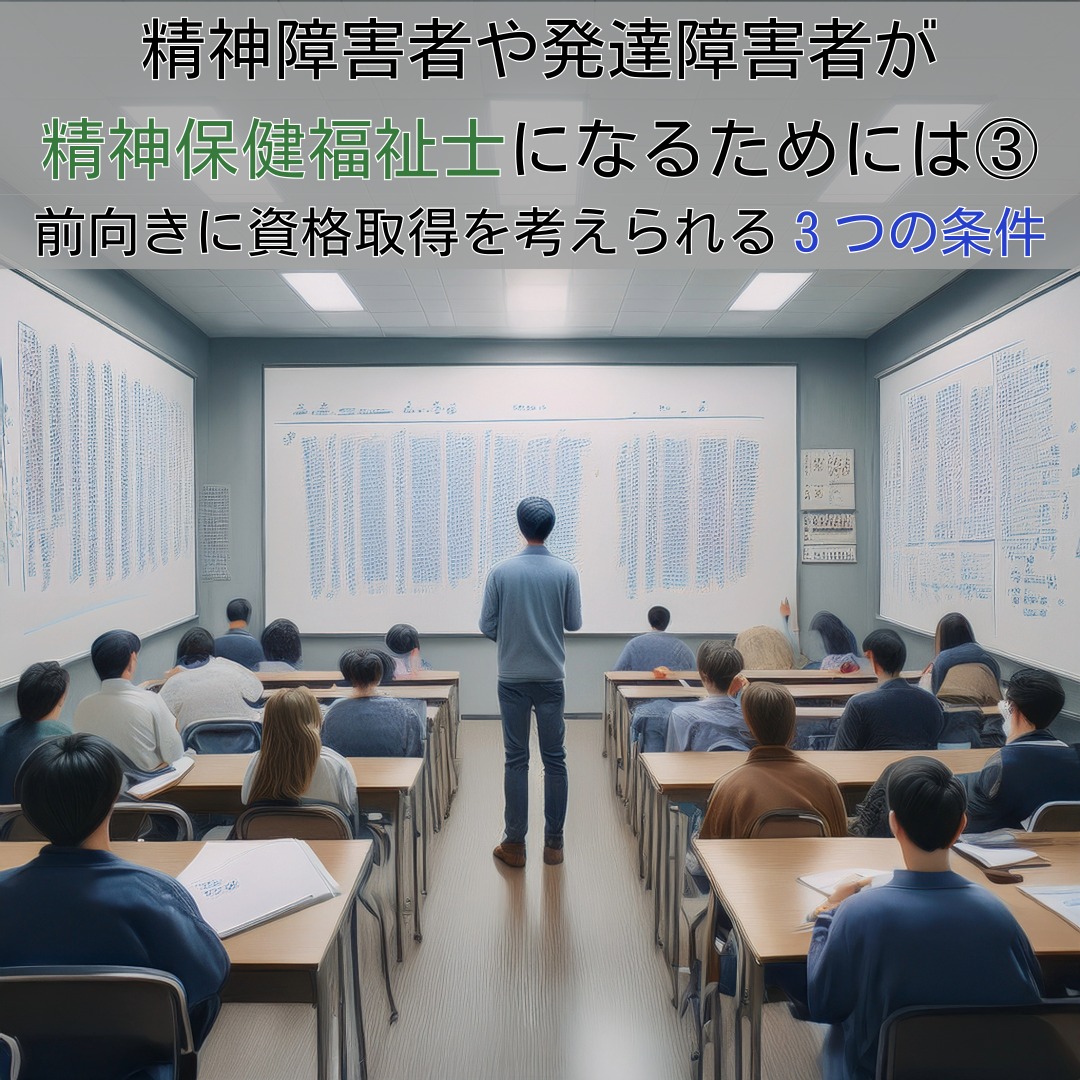





コメント