自らの周りや環境にひそむ困難さ
自分自身だけでは乗り越えられない難しさもある
精神障害や発達障害の当事者である精神保健福祉士にとっては、自ら乗り越えなければならない困難さだけではなく、自分の努力だけではどうしようもない「障壁」もある。
私は少なくとも次の3つのような障壁があると感じている。
- 職場の理解を得てうまくやっていけるか
- 環境や制度のバリア
- 当事者特有のキャリア形成の難しさ
1つ目:職場の理解を得てうまくやっていけるか
精神障害者・発達障害者の精神保健福祉士がどこかの職場に所属して活動する場合、その職場から理解を得られるかは極めて重要である。
ところが実際には以下のような問題がある。
いわゆる合理的配慮について相談することで、「支援者としての適格なのか」と職場側から受け取られる不安を感じるかもしれない。
また精神保健医療福祉の現場で働く場合、自らが利用者・患者と同じような病気・障害を持ちながら働くことになる。
特にこの場合に上司や同僚が
「普段利用者・患者として接する『こころの病気や発達障害を持つ人』と一緒に働くこと」
に抵抗感を持つということもありうる話である。
2つ目:環境や制度のバリア
社会的な障害者雇用の取り組みは進んでいるものの、福祉専門職として働きたい精神障害や発達障害の当事者の精神保健福祉士にとっては、次のようなバリアがある。
この背景には、病気・障害の当事者が支援の担い手になることに対する違和感・警戒感があることも考えられる。
3つ目:当事者特有のキャリア形成の難しさ
精神保健福祉士は日々の経験や定期的な研修の受講などを通じて、キャリアを積み重ねていく必要がある。また専門性を高め、研鑽を続けることが求められる。
ところが精神障害や発達障害を持つ精神保健福祉士には、健常者の精神保健福祉士にはない次のような課題がある。
これらは病気・障害を持つ自分を大事にしながら精神保健福祉士として活動し続けることに対する難しさといえる。
リンク



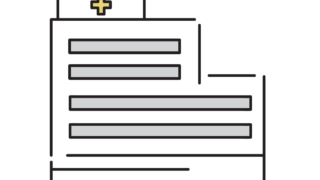



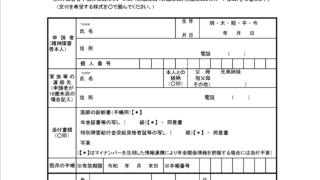
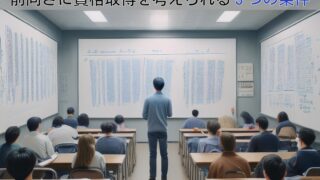









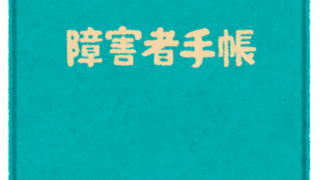
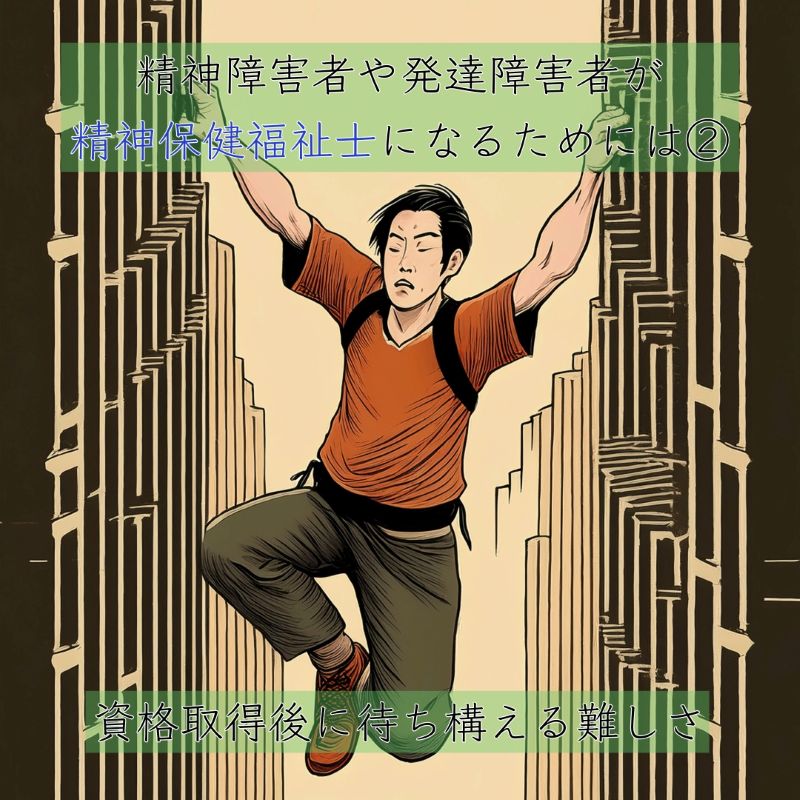


コメント