本人自身にある困難さ
様々考えられる難しさ
精神障害や発達障害の当事者が無事に精神保健福祉士の国家資格を取得した後、実際にこの資格を活かして活動していくためには、私がすぐ思いつく範囲だけでも以下のような困難さがある。
- 利用者や患者と十分コミュニケーションを取れるかどうか
- 自らの病気や障害をどう捉えるか
- 自分自身のメンタルケアができるか
もちろんこれら3つ以外にもあるかもしれない。ここからはこの3つをそれぞれ具体的に説明する。
1つ目:利用者や患者などと十分コミュニケーションを取れるかどうか
そもそも精神保健福祉士は「こころに何らかの傷を抱える人々」と関わる機会が多い。そのためその立場上、常に高度で繊細なコミュニケーションを取る必要がある。
もちろん福祉施設の利用者や精神医療を受ける患者との意思疎通について、通学していた大学・専門学校で学んだはずである。学校の教科書に書かれていた内容や実習で確認したことを思い出しながら取り組まなければならない。それに加えて自らの病気・障害の経験から分かることもあるだろう。
ところが実際の精神保健医療福祉の現場においては、自身の病気・障害の特性により、次のような事態に遭遇する可能性がある。
「どう頑張っても学んだこと・自らの経験が活かせず、利用者や患者とうまくコミュニケーションが取れない。」
精神保健福祉士としてふさわしいコミュニケーションが取れなかった結果、相手を精神的に傷つけることや、逆に自らのこころを痛めてしまう事態が起こりうる。
例えば以下のようなことは健常者の精神保健福祉士でももちろんあるが、精神障害や発達障害を持つ場合は特に気を付けて欲しい。
2つ目:自らの病気や障害をどう捉えるか
精神障害や発達障害を抱える精神保健福祉士にとっては、以下も難しいことになりうる。
「自らの病気や障害をどのように捉えているか。」
精神保健福祉士が支援する主な対象者は、精神障害や発達障害を抱える人々である。このような病気・障害を卑下する精神保健福祉士はいないと私は思いたい。
ただ病気や障害のある人の中には、次のように感じる人もいる。
「自分は健常者と比べてどうしても劣っている。」
ひょっとしたら、精神障害や発達障害の当事者である精神保健福祉士の中には、いわばこのような「病気・障害による劣等感」と闘う人がいるかもしれない。
だが私はこれを支援対象の相手に持ち込むべきではないと考える。そのためには、自らの病気や障害を受容する必要がある。
「他人と比較する必要はない。自分らしく活動しよう。」
と思えるようになれば、支援の相手になる利用者・患者にもこの思いが伝わるはずである。
同じように病気・障害を抱える利用者・患者の受容や「生きやすさ」にもつながる。
3つ目:自分自身のメンタルケアができるかどうか
もう少し分かりやすく言うと、次のようになる。
「自分自身で自らの心の健康を保てるかどうか」
精神障害を抱える精神保健福祉士で、メンタルヘルスのもろさを抱える人はおそらく多い。発達障害を持つ精神保健福祉士も同様かもしれない。このことも困難さになるはずである。
このような病気・障害を抱える精神保健福祉士特有のこととして、同じような病気・障害で悩む患者や利用者と会話を重ねるうちに、相手と自らそれぞれの病気・障害や生きづらさを重ね合わせる機会がどうしても生まれる。
それによって支援を行う自分自身がつらくなることやこころが傷つくこともある。
例えば次のような経験をするかもしれない。
「私自身もこの人と同じようなつらい体験があった。思い出して私もつらくなる。」
もしそうなれば、ただでさえもろさを抱えている自らのこころにダメージが加わり、自分自身の精神が容易に病んでしまうのである。
このような事態にならないように、精神障害や発達障害を持ちながら活動する精神保健福祉士は、健常者の精神保健福祉士以上に次のような能力を身に付ける必要がある。






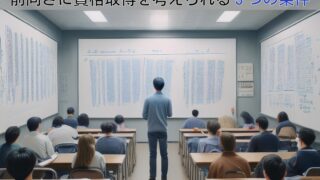
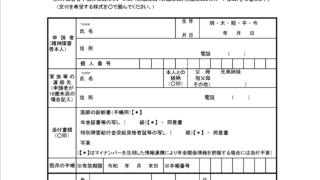


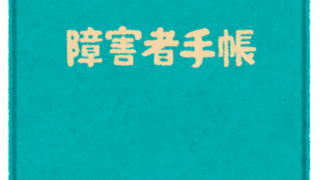






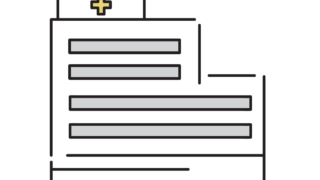

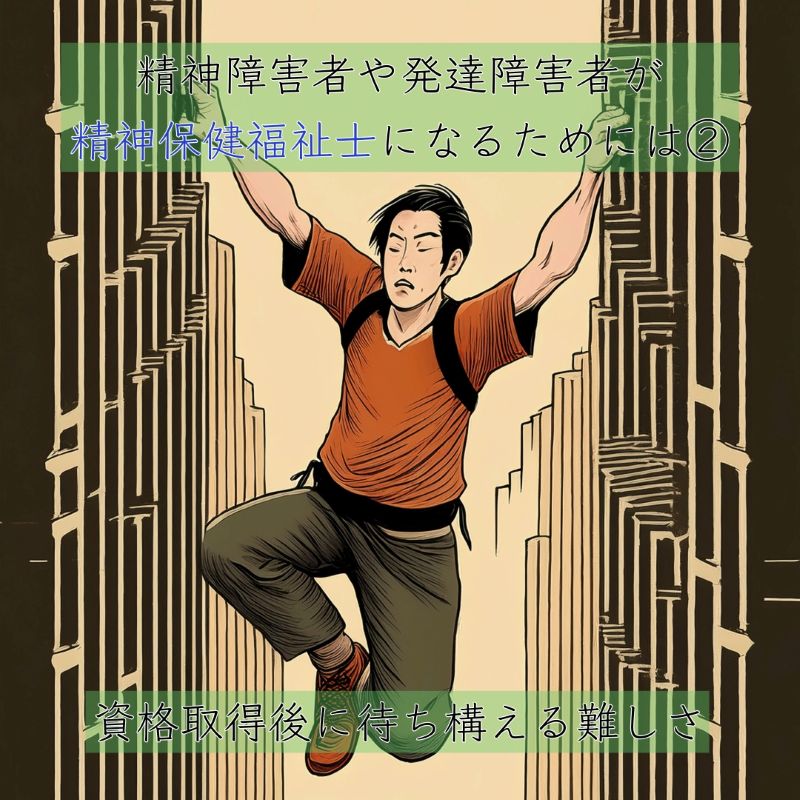


コメント