2026年1月20日更新
- 1ページ目:見出しや本文の順番の入れ替え
- 小見出しの追加や、文章の追記・修正
- 記事末尾の記事リンク集の変更
2025年9月17日更新
- 「精神障害者保健福祉手帳の解説シリーズ」の記事リンクを掲載しました。
- 本文の一部を修正・変更しました。
- 記事の「タグ」を追加しました。
はじめに
こころの病気に対応する精神障害者保健福祉手帳
日本では、何らかの障害のある人に対して、以下の3種類の「障害者手帳」を発行している。
- 身体障害者手帳:視覚・聴覚・肢体不自由など身体の障害
- 療育手帳:知的障害
- 精神障害者保健福祉手帳:精神疾患(発達障害含む)
そのうち、統合失調症・双極性障害・うつ病といった「こころの病気」を持つ人に対して発行されるのは、「精神障害者保健福祉手帳」(精神障害者手帳)である。
この手帳について、ひょっとしたら以下のように感じる人がいるかもしれない。
この記事では、精神障害者保健福祉手帳のことを初めて聞く人・あまりよく分からない人・迷っている人向けに、だいたいの内容をできるだけ分かりやすく説明する。
一部「取り上げる必要はあるがやや難しい」と思われる内容もある。これについては、区別できるように文字の背景色をグレーに変更している。
当記事の要旨
- 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神疾患や発達障害(神経発達症)によって日常生活・社会生活に支障を抱える人が取得でき、生活を支える様々な制度・サービスが利用できる。
- 精神障害者保健福祉手帳は、「等級の大まかな目安」「手帳を持つメリット」「取得方法」など、事前に理解しておきたいことがいくつかある。
- 今後も精神障害者保健福祉手帳の存在・正確な情報を提供することで、必要な人がこの手帳を取得しやすい環境作りに努めたい。
当記事を読んで欲しい人
当記事のこの後の流れ
2ページ目:精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳について、対象者・等級・手帳を持つことによるメリット・取得方法を中心に説明している。
3ページ目:まとめ
当記事の内容をまとめるとともに、精神障害者保健福祉手帳の存在や正確な情報を提供することで、よりこの手帳を取得しやすい社会作りをすべきという趣旨のことを書いている。
「福祉ウォッチャーT」では、過去にも以下の「精神障害者保健福祉手帳」関連の記事を投稿済みです。ただいま最新の状況を盛り込みつつ、より理解しやすくなるようにリニューアルしています。当記事はその一環です。
2025年9月17日追記:精神障害者保健福祉手帳の解説シリーズ記事一覧はこちらから
リンク




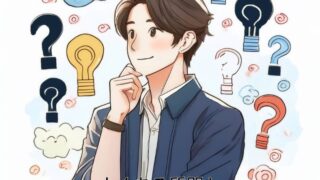


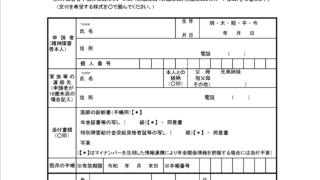


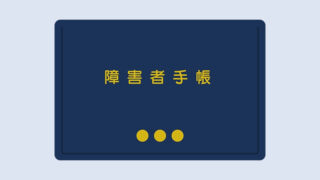








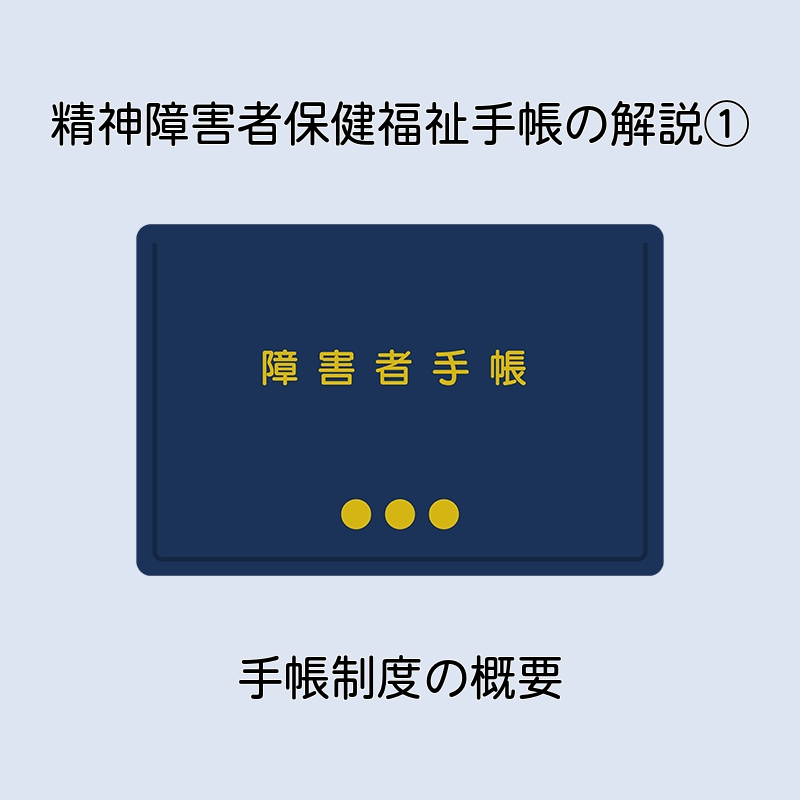

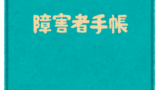









コメント