まとめ
「不登校専門クリニック」は分かりやすい
私は不登校に対応するために、医療的・社会的双方の取り組みが必要だと考えている。そのうち医療の取り組みについて、「不登校専門クリニック」を開設した飯島氏の手法は、大胆かつ分かりやすいのは間違いないだろう。
ただ不登校の問題に取り組む医師の数が課題だろう。子どもの精神疾患や発達障害に精通する児童精神科医が少ないという問題は近年よく言われている。現に発達障害の診断を長期間待つ子どもやその家族の話をたまに聞く。
私自身は医療の専門家ではないので、医療職の養成に関してはあまりコメントできない。それでも不登校を経験した私としては、児童精神科医や子どもの精神疾患に関する基本的な理解を持つ医師がより増えて欲しいと思う。
子どもの精神疾患を理解する医師の増加は、不登校を経験する子どもの「生きづらさ」を、成長に伴って増幅させないようにする観点からも大事ではないかと考えている。
最後になるが、不登校の問題や子どもの精神疾患の社会的理解の促進に向けて取り組まれている飯島氏について、私は立場は違うものの興味関心を持って見ていきたいと感じた。

自閉スペクトラム症の子どもの特性・関わり方についての記事を見て【ニュース紹介4】
ASD(自閉スペクトラム症)を持つ子どもの特性・関わり方を解説したニュース記事の紹介と、この記事に関する私の経験・考えについて。

【発達障害】4月2日は世界自閉症啓発デー→生きづらい自閉症(ASD)の理解を深めるために
自閉症(ASD)に関する簡単な説明と生きづらさ、世界自閉症啓発デーに関する話題提供、自閉症の理解を深めるための筆者の持論

【精神科・心療内科】私の思う主治医とのより良いコミュニケーションの取り方(+α)【診察時】
筆者の実体験を基にした主治医との上手なコミュニケーションの取り方について(特に精神科・心療内科)

【障害当事者視点】私が思う福祉職員・心理職員など支援者との上手い関わり方
障害当事者がどうすれば支援者と上手に関われるのか、ということについての筆者の考え。私自身の経験を含む。

精神保健福祉士の精神疾患当事者が「クローズアップ現代」(2月12日放送分)を見て【心の病・精神障害】
心の病(精神疾患・精神障害)について取り上げたNHKの「クローズアップ現代」(2025年2月12日放送分)を見た感想と、心の病当事者として今後の要望
リンク












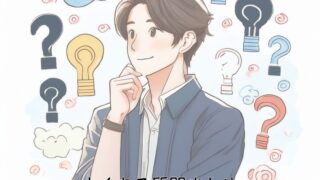


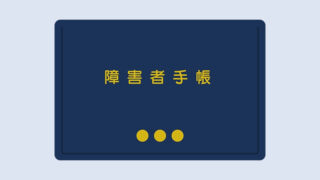
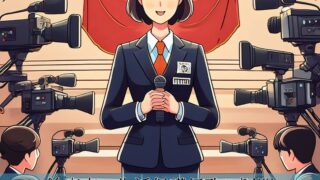





コメント