まとめ
合理的配慮の理解を深めるために
障害当事者・事業者・社会の三者の理解が必要
私は障害者差別解消法のいう合理的配慮について、配慮を受ける障害当事者側も、配慮を提供する事業者側もお互いに納得できる方が良いと考える。
そのためには、まずこの合理的配慮の法的定義を両者ともに十分理解しなければならない。それに加えて障害者や事業者の置かれる社会の理解も必要不可欠だろう。
社会的理解が不十分だからこそ、合理的配慮を求めたり提供を受けたりする障害者が「過剰な要求」や「クレーム」などと「不当な」非難の対象になってしまう。
それでは障害者が委縮してしまい、合理的配慮を求めづらくなる。さらにいえば、そのような社会の雰囲気自体が障害当事者にとっての「障壁」や「バリア」になる。
その結果、障害者が社会から締め出され、障害者差別解消法が目指す
- 障害者差別の解消
- 共生社会の実現
からかえって遠ざかるのである。
この状況を変えるためには、政府や地方自治体がより啓発活動に取り組まなければならない。改正障害者差別解消法が施行される2024年4月は、政府や地方自治体などがより啓発活動に力を入れる良い機会になると私は考えるが、どうだろうか。
「障害者に関する世論調査」を見て
実際内閣府が令和4年(2022年)11月から12月にかけて実施した「障害者に関する世論調査」によると、障害者差別解消法を「知っている」と答えた人が24.0%(小計)※1、「知らない」と答えた人は74.6%だった。(内閣府 2023:22)
また障害のある人に対する配慮や工夫が行われない場合、障害を理由にした「差別に当たる場合があると思う」と答えた人が64.7%(小計)※2、「差別に当たる場合があると思わない」と答えた人が33.1%(小計)いた。※3(同書:26)
この結果より、障害者差別解消法をそもそも知らない人が、全体のほぼ3/4を占めている。それと合理的配慮を提供しないことが差別になると思わない人が、全体の3割以上もいるのである。
注釈について
※1:「法律の内容を、改正法の内容も含めて知っている」(2.0%)・「内容は知っているが、改正されたことは知らない」(3.7%)・「内容は知らないが、法律があることは知っている」(18.3%)の合計
※2:「差別に当たる場合があると思う」(26.8%)・「どちらかといえば差別に当たる場合があると思う」(37.9%)の合計
※3:「どちらかといえば差別に当たる場合があると思わない」(17.1%)・「差別に当たる場合があるとは思わない」(16.0%)の合計
国や地方自治体は理解を促す取り組みを
やはり国や地方自治体は、合理的配慮を定義する障害者差別解消法の存在や、障害者に対する合理的配慮の提供が法的に必要なことを、今一度社会に向けて周知しなければならない。
その上で、社会全員が合理的配慮の定義を正しく理解できるように、国や地方自治体が啓発しなければならない。それを続けることで、障害者がより安心して社会で暮らせるのではないかと私は考える。
- 内閣府(2023)「『障害者に関する世論調査』の概要」(2024年4月10日アクセス)
https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-shougai/gairyaku.pdf
最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ以下の記事もあわせてご覧ください。
障害者差別解消法に関わる他の記事はこちらから
その他こちらの記事も関連するかもしれません。


または「テーマ別ブログ記事まとめ」にお進みください。


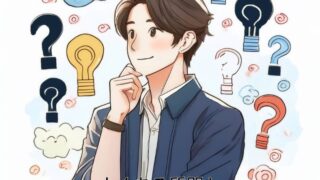

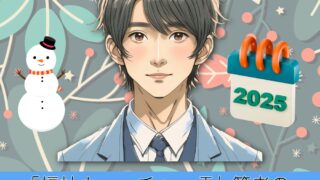




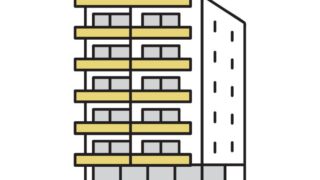



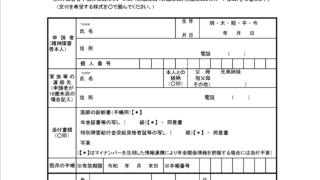




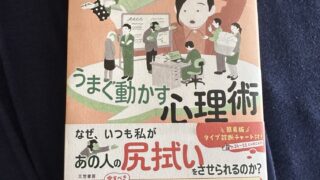





コメント