まとめ
「保険料『未納』→障害年金不支給リスク」に対して私たちができること
年金保険料は払う方が良い。老後の保障だけではない。
年金保険料の「未納」により、障害年金がもらえずに後悔する人がいる。年金保険料の負担は確かにある。しかし老後だけでなく心身の障害に対する備えにもなることを考えると、できれば払う方が良いと言える。(さらにいえば遺族年金もある)
年金保険料の支払いが難しければ、免除や猶予の申請を
もし経済的に困窮しており年金保険料の支払いが困難な場合は、免除や猶予の手続きを忘れずに取って欲しい。それと現在年金保険料の「未納」がある人は、至急健康なうちに追納するか免除・猶予の申請をして欲しい。
国や日本年金機構もできることがまだありそう
障害年金の周知徹底が必要ではないか
このことに関連して、国や日本年金機構にも課題がある。やはり障害年金の存在をもっと国民に周知すべきである。
例えば公的年金制度に加入する20歳の人に送付している「国民年金加入のお知らせ」の書類に、障害年金のことをより明記すべきである。特に受給要件を満たせば、20歳からでも障害年金をもらえることを載せて欲しい。
それに加えて以下のような具体的な説明を掲載することも有効ではないか。
- 交通事故によって若くして身体が不自由になった場合、障害年金が一定の経済的保障になる。
- ストレスによって生じたこころの病気がなかなか治らない場合も障害年金の対象になる。
- がんや糖尿病でも障害年金がもらえる場合がある。
- 年金保険料の納付が困難な場合も免除・猶予にすれば障害年金の受給要件には影響しない。
年金セミナ―は工夫して続けて欲しい
他には高校や大学・専門学校における周知を工夫しながら継続して欲しい。特に年金セミナーの取り組みは今後も続けつつ、学校側の協力を得て公的年金制度を説明するパンフレットを学校窓口に常備するなどの取り組みを進めて欲しい。
またマスメディアやYouTube等での広報も重要になる。例えば各種年金関連のパンフレットにYouTube動画に飛ぶリンクのQRコードを掲載できるのではないか。
「ねんきん定期便」での案内
さらに30代や40代の国民への対応として、「ねんきん定期便」に障害年金の案内を載せることも検討して欲しい。
「ねんきん定期便」はこれまでの年金記録の確認や老齢年金の支給見込み額の案内が主な役割である。ただ35歳・45歳の人向けのねんきん定期便は封書で郵送される。その封書に障害年金の案内チラシを入れることもできる。
なお私が最近受け取った「ねんきん定期便」の封書には、障害年金に関する案内はなかった。「ねんきん定期便」における障害年金の案内は過去にあったようだが、今後は確実に盛り込んで欲しい。
例えば2017年度(平成29年度)の「ねんきん定期便」には、障害年金の案内が掲載されていた。
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/kako/2017/201701.files/29-11-2.pdf
最後に…
障害年金制度についてより詳しく周知するだけでも、国民の年金保険料未納や障害年金不支給のリスクが減るのではないか。さらには国民の公的年金制度に関する信頼を多少でも取り戻すことになるかもしれない。
- 内閣府(2024)「『生活設計と年金に関する世論調査』の概要」(2024年4月18日アクセス)
https://survey.gov-online.go.jp/r05/r05-nenkin/gairyaku.pdf - 日本年金機構(2023)「知っておきたい年金のはなし」(2024年4月19日アクセス)
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/seminar.files/kougigataR5.pdf - 日本年金機構(2024a)「国民年金の加入と保険料のご案内」(2024年4月19日アクセス)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/3.pdf - 日本年金機構(2024b)「障害年金ガイド 令和6年度版」(2024年4月18日アクセス)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf






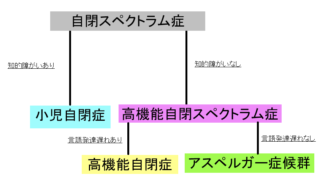



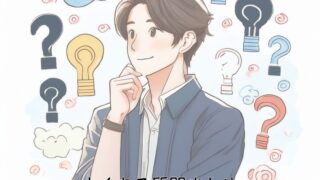


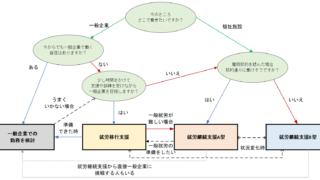













コメント