障害者差別解消法のいう合理的配慮とは
障害者差別解消法の簡単な経緯と概要
障害者差別解消法の成立(WAMNET 発行年不明)
日本政府は2007年9月に署名した「障害者の権利に関する条約」の批准に向けて、2009年12月に「障害者制度改革推進本部」を内閣に設置した。
推進本部やそれを引き継ぐ形で設置された障害者政策委員会における議論を踏まえ、2013年4月に政府が「障害者差別解消法」の案を閣議決定し、第183回通常国会に提出した。その後衆議院・参議院両院で可決・成立され、2013年6月26日に障害者差別解消法が公布された。
この法律は、障害者基本法第4条「差別の禁止」の規定を具体的に定めたものであり、
- 障害者差別の解消
- 共生社会の実現
が目的になっている。それと法律に基づき差別解消を支援する各種措置が行われることになった。
障害者差別解消法により、障害を理由とした「不当な差別的な取扱い」が禁止された。また行政機関等に対しては「合理的配慮の提供」の義務が課された。ただし民間事業者に対しては、合理的配慮の提供の「義務」までは課されず「努力義務」止まりだった。
当初は法的義務ではなかったため、民間事業者は障害者に対して合理的配慮をしなくても一応法的には問題にならなかった。
障害者の雇用や就労に関する差別解消は、障害者差別解消法ではなく「障害者雇用促進法」に規定されている。
| 行政機関等 | 民間事業者 | |
| 不当な差別的取り扱い | 法的義務 | 法的義務 |
| 合理的配慮の提供 | 法的義務 | 努力義務 →法的義務 (2024年4月より) |
障害者差別解消法の改正・施行(内閣府 発行年不明c:2-3)
障害者差別解消法は2021年(令和3年)に改正され、2024年4月より施行された。この改正で民間事業者の合理的配慮提供の「努力義務」が「義務」になった。つまり2024年4月以降は、民間事業者も合理的配慮を行わなければ法的な問題になる。
したがって民間事業者も、障害者から合理的配慮を求められれば提供できるように対応しなければならないのである。
合理的配慮のポイント
「バリア」「障壁」を取り除き、健常者と同等の条件にする配慮(同書:4-5)
地域社会にある施設・サービスの中には、障害者の利用を前提としていないものがある。障害のある人がそのような施設・サービスを利用しようとした場合、実際には利用できなかったり利用に制限を受けたりすることがある。
その際利用者が、このような「バリア」や「障壁」といえるものを取り除くように施設運営者やサービス事業者に求める場合がある。
この場合、運営者や事業者は、
負担が過重にならない範囲で、障害のない人と同様に施設・サービスを利用できるように必要かつ合理的な配慮を行う
義務がある。これが障害者差別解消法のいう合理的配慮の提供義務である。
合理的配慮には欠かせない「建設的対話」(同書:6-7)
事業者側が合理的配慮の提供を具体的に検討する際には、障害当事者と建設的に話し合う必要がある。(建設的対話)
時に事業者側が、当事者の要求をそのまま受け入れると、負担が過重になる場合や合理的でなくなる場合がある。その場合でも事業者側がその事情を可能な限り当事者に納得してもらえる形で説明し、代替案を一緒に考えることが求められる。
もし事業者側がこの建設的対話を一方的に拒むと、合理的配慮の提供義務に反することになる。
という理由で合理的配慮の提供を断ることも、法的な問題になることに注意が必要である。
事業者が障害者に行う合理的配慮の事例をまとめたWebサイト「合理的配慮サーチ」を内閣府が用意している。興味のある人は参照して欲しい。
合理的配慮の要求と「クレーム」の違い
先ほど述べた通り、障害者が障害のない人と同様に施設・サービスを利用するために、事業者側に対して「バリア」と感じるものを取り除くように表明することは、合理的配慮の要求といえる。
ただ実際には事業者側にとってどうしても負担が重すぎるため、そのままではこの求めに応じられないことがある。だからといってそれは障害者の「過剰な要求」や「クレーム」とはまったく異なる。
障害のある人が障害者差別解消法で定義される「合理的配慮」を求めることは、以下のような「障害者の特権」を主張することとはまったく違うのである。
例えば自力で移動できる車イス利用者が、飲食店を利用しようとする際に、車イスに座ったまま利用するためにイスを移動できるかどうか相談することは、合理的配慮の要求といえる。
その車イス利用者が「つきっきりで車イスを押して」などと、店員に不要かつ過剰な介助を求めることとは訳が違う。
それと精神や発達の障害者の中には、音に敏感のため静かな環境が必要な人もいる。その人が「施設内の静かな場所で休めるか」と合理的配慮が可能か相談することは、「他の利用者を追い出して欲しい」といった事業者側にとっての無理な要求とはまったく別物である。
要するに、私たちは合理的配慮の要求とそれ以外の過剰な要求などを区別して理解しなければならない。
両者を同一視すれば、障害当事者はたとえ「バリア」や「障壁」を感じても、社会からの非難を恐れて必要な声すら上げづらくなってしまう。そうなれば障害者の社会的排除にも直結してしまうのである。
| 項目 | 合理的配慮の要求 | クレームや過剰な要求 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 障害者差別解消法 | 法的根拠なし |
| 目的 | 障害による不利益の解消 | 個人的利益の追求 |
| 実施の判断 | 合理性や過度な負担の有無 | 要求の妥当性が不明確 |
- WAMNET(発行年不明)「『障害者差別解消法』制定までの経緯と概要について」(2024年4月8日アクセス)
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/appContents/wamnet_skaisyou.html - 内閣府(発行年不明a)「合理的配慮等具体的データ集 合理的配慮サーチ」(2024年4月8日アクセス)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/ - 内閣府(発行年不明b)「平成28年4月1日から障害者差別解消法がスタートします!」(2024年4月10日アクセス)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai/leaflet-p.pdf - 内閣府(発行年不明c)「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(2024年4月10日アクセス)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf

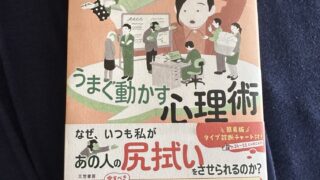



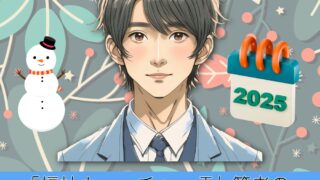
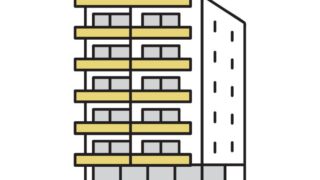


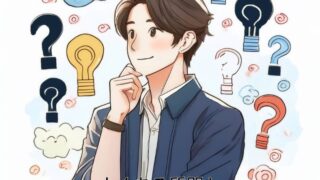




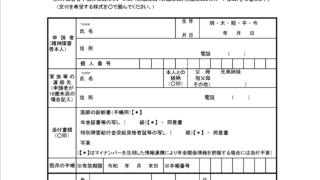








コメント