まとめ
「利用者とは対等」だからこそ得られるものもある
障害者の「作業所」(ここでは就労継続支援A型・B型)における職員の役割は、障害のある利用者が主体的に働けるように支援することである。いわば「舞台の裏方」に近い役割なのだが、利用者と一緒に働く以上はときに利用者に助けてもらうこともある。
確かに利用者と職員という役割の違いはある。だが職員の方が「利用者より上の立場」では決してない。利用者も職員も「対等な立場」で一緒に働いているのである。
このような「立場の対等性」や「支援するばかりではない」ということは、障害者の「作業所」だけに限った話ではない。
例えば高齢者の福祉・介護の現場では、職員が高齢者を支援するだけではなく、支援相手の高齢者から
経験もあるはずである。職員側から見れば、高齢の利用者に「助けてもらった」と言えそうである。
それと児童福祉の現場で働く職員は、子ども同士のトラブルに対応するばかりでなく、元気に動き回る子どもを見て、職員自身も元気になることもあるはずである。
したがって福祉の仕事は、得られるものや助けてもらえる時があることを考えると、決してしんどいことばかりではないと私は考えている。
最後に:福祉の仕事はしんどいことばかりではなく、楽しいこともある
福祉の仕事は、他人とのコミュニケーションや他の職員との協働が十分できないと困難な仕事であることは事実である。その一方で支援の相手になる利用者との関わりを通じて、楽しさ・面白さを感じることもある。さらに利用者から元気をもらうなど、
「支えるはずが支えられる」
こともある。
そう考えると、私は福祉の仕事は決して悪くないと思っている。もちろん人によって仕事の向き・不向きはあるだろうが、私にとっては
という意味で、福祉の仕事・福祉施設(B型作業所・就労継続支援B型事業所)での仕事を実際に経験して良かったと感じている。





「トゥギャザーオンラインショップ」は、全国の障害者福祉事業所が作る「こだわりの」食品・雑貨を扱うWebサイトです。
オンラインショップなので、お家にいながら気になる商品を取り寄せられることは当然ですが、取り扱う商品は各地の障害者福祉事業所の利用者が丁寧かつ一生懸命作っています。それだけではなく、健常者が作るような他の商品以上に見た目や品質に「こだわった」商品です。
食品であれば、「自分へのご褒美」や「気持ちのこもった贈答品」としても十分な味・見た目です。また雑貨・おもちゃ
についても、作り手の個性やクリエイティブさが表れています。
もちろん「トゥギャザーオンラインショップ」での購入を通じて、障害のある人の生活保障・収入にもつながります。まずは一度実際に手に取って試してみませんか?











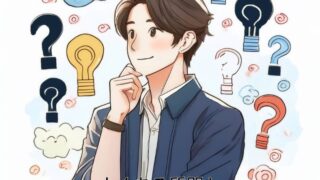





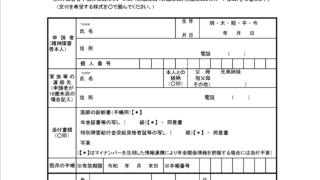

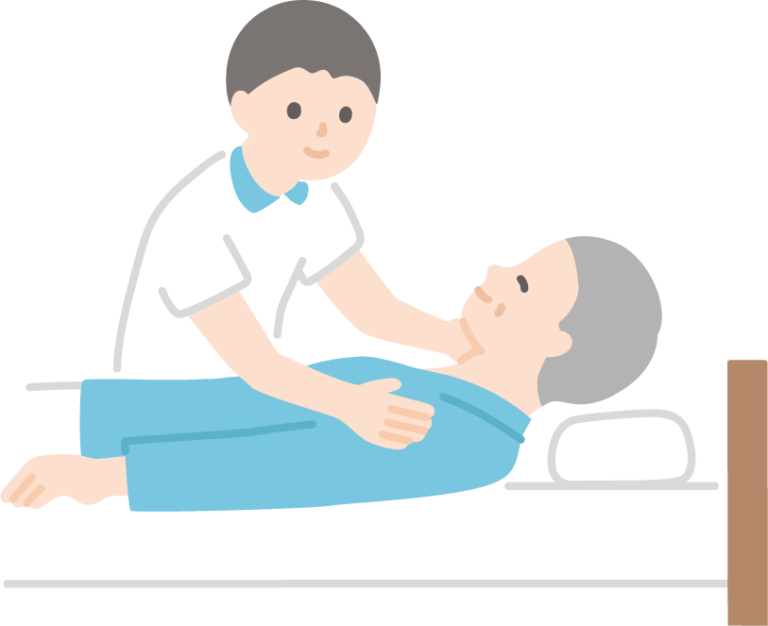



コメント