2025年7月31日更新
- 本文や見出しを一部追記・修正しました。
- 3ページ目の「最後に…」セクションに箇条書きを追加
- 「はじめに」の部分に「この記事をぜひ読んで欲しい人」のセクションを追加しました。
- 「タグ」を追加しました。
はじめに
当記事の要約
- 精神科病院の地域と連携した社会復帰・地域移行に関する取り組みを聴き、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を実現するためには、地域精神医療に貢献する形への精神科病院の方針転換が強く求められることが分かった。
- 発達障害(神経発達症)のピアサポート活動に関係して、「普通っぽく生きる」ことではなく「自分自身に素直に生きられる」ようになることが自身の発達障害の受容と言えそうである。それとピアサポートを通じて障害の受容について伝えることも重要だと認識した。
- 精神科医など精神医療従事者は、今後の日本の精神医療を改善するためにより精神障害・発達障害当事者の声を聴き協働することが不可欠だと考える。一方精神障害・発達障害当事者側もより声を上げることが行政や社会を動かす原動力になる。
この記事をぜひ読んで欲しい人
- 日本の精神保健医療福祉に課題を感じている関係者(精神医療従事者・当事者含む)
- 「第121回 日本精神神経学会学術総会」の参加者
当記事について

2025年6月19日(木)から6月21日(土)までの3日間にわたり、神戸市内で「第121回日本精神神経学会学術総会」(学術総会)が開催された。
私はそのうちの3日目に参加し、次の2つのシンポジウムをそれぞれ拝聴した。
- 「『精神障害にも対応した地域包括ケアシステム』を支える精神科病院の役割」
- 「神経発達症におけるピアサポート~医療と自助活動との接点を探る」
当ブログ記事では、この度私が参加した学術総会やシンポジウムの感想を述べる。それと学術総会・シンポジウムの参加を踏まえて、当ブログ記事を書く時点(2025年6月27日)での私見を述べる。
当記事の構成
2ページ目:実際に参加しての感想
私が実際に参加した2つのシンポジウムを中心に、「第121回日本精神神経学会学術総会」3日目の感想をできる範囲で具体的に書く。
3ページ目:日本精神神経学会学術総会参加を踏まえて今思うこと
学術総会3日目への参加を振り返って、当ブログ記事を書いている現在私が思うことをまとめている。
リンク


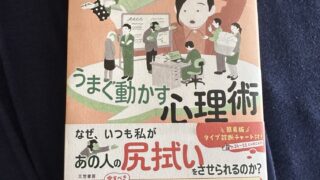
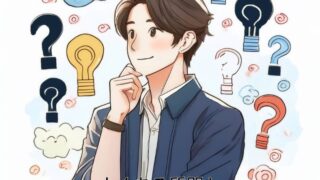






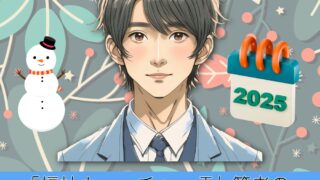
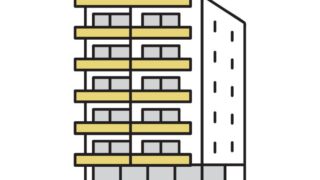






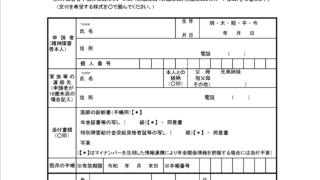



コメント