実際に精神障害者保健福祉手帳を持って良かったこと②――心理面・社会面
心理・社会面で良かった4つのこと
心理面や社会面でも、この手帳を持っていて良かったことが4つある。
- 「見えない障害」が可視化されること
- 支援や配慮が求めやすくなること
- 社会参加や日常生活のハードルが下がること
- 同じ手帳を持つ人との連帯が生まれること
ここでは、上記の4つを具体的に述べる。
①「見えない障害」が可視化されること
精神障害・精神疾患や発達障害(神経発達症)は、外見からは分かりにくい。「見えない障害」とも言われる。
精神障害者保健福祉手帳を持てば、少なくとも手帳がない状態よりは、日々の生活における困難や、配慮の必要性が社会的に認められ、伝わりやすくなったと思う。
「説明しても理解されにくい」状況が多少は和らいでいる。
②支援や配慮が求めやすくなること
①と関連するが、手帳があることで、職場や学校、行政機関などに支援を求めやすくなった。それに加えて、支援や配慮を求めることの心理的なハードルが下がったように感じる。
③社会参加や日常生活のハードルが下がる
手帳を持つことで受けられる割引や助成などのサービスを通じて、少しは外出やイベントへの参加がしやすくなった。「外に出よう」「イベントに行こう」と思えるきっかけにもなり、社会とのつながりを保てている。その結果、社会からの孤立・排除をまぬがれている。
④同じ手帳を持つ人との連帯が生まれること
私は現実の場やインターネット(特にSNS)で、同じ手帳を持つ人とつながる機会がある。同じような悩みや経験を共有できることで、連帯が生まれている。
また、手帳を持っていること自体が、話題や共感のきっかけにもなる。「悩んでいるのは自分だけではない」と思え、孤立感の緩和や安心につながっている。
リンク



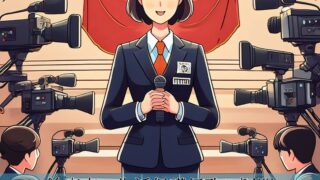


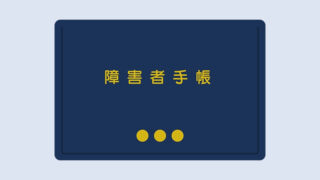









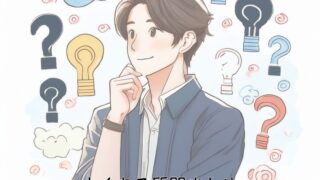





コメント