はじめに
精神障害者保健福祉手帳はただの「証明書」なのか
精神障害者保健福祉手帳は、各種福祉制度・サービスを使うための「証明書」として利用する人が多い。しかし、私自身は実際に持ってみて、この手帳にはそれ以上の意味があると感じている。
これまで当ブログ「福祉ウォッチャーT」では、手帳の制度的なメリットや使いやすさについて、以下の記事で紹介してきた。
今回は少し視点を変えて、私自身が手帳を持っていて助かったこと、ありがたいと感じたことをまとめる。制度・サービス面だけでなく、社会生活や心の面でのメリットについて、当事者として実感したことをお伝えする。
本記事が、精神障害者保健福祉手帳の取得を検討している方や、手帳の存在を周囲に伝える立場の方にとって、少しでも参考になれば幸いである。
この記事の要旨
- 私自身が精神障害者保健福祉手帳を持って良かったことを、制度・サービス面と心理・社会面の2つの側面からまとめている。
- 制度・サービス面では、医療費助成や税金の減免、交通運賃割引など、6つのメリットがあると感じている。
- 心理・社会面では、「見えない障害」が可視化されることや、支援や配慮を求めやすくなることなど、良かったことを4つ挙げている。
- 手帳は、制度的な支援だけではなく、心理的・社会的な側面でも生活を支えている。
この後の流れ
2ページ目:実際に精神障害者保健福祉手帳を持って良かったこと①――制度やサービス面
私が手帳を持って良かったことのうち、各種制度・サービスに関わるものを6つ取り上げ、具体例を交えて説明する。なお、公的・民間問わずまとめて掲載している。
3ページ目:実際に精神障害者保健福祉手帳を持って良かったこと②――心理面・社会面
同様にして、私が手帳を持つことで感じた心理的・社会的なメリットを4つ取り上げ、当事者としての経験を交えて説明する。
4ページ目:まとめ
制度・心理の両面を振り返り、当記事の内容を総括する。さらに当記事の読者へのメッセージもある。ぜひ最後までご覧いただきたい。
リンク


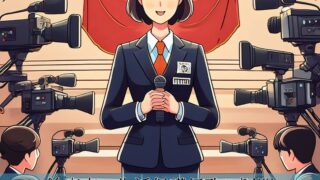


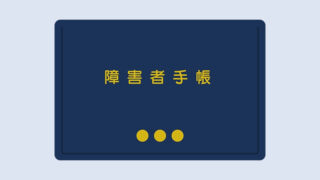







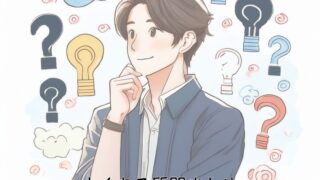










コメント