2025年3月29日更新
- 「当記事の更新情報」をトグルボックスにしました。
- クリックすれば内容を確認できます。
- タイトルを再度修正しました。
- 旧タイトル:【精神科・心療内科】主治医とのより良いコミュニケーションの取り方(+α)【診察時】
- より読みやすくするために本文を一部加筆・修正しました。
- 文字修飾の変更
- リスト表示の追加など
- 「タグ」「カテゴリー」をそれぞれ追加しました。
2024年6月14日更新
- タイトルを修正しました
- 旧タイトル:「【精神科・心療内科】主治医とのコミュニケーションの取り方(+α)」
- 見出しを追加しました
- 本文に必要なことを追記しました
- 読みやすくなるように修正しました
はじめに
当記事の要旨
- 精神科や心療内科で、比較的短い診察時間でうまく主治医とコミュニケーションを取る方法の一つは、事前に伝えたいことをまとめておくことである。
- 主治医からの言葉は十分尊重すれば良いが、どのように治療を進めるかを最終決定するのは患者自身である。
- 主治医と十分意思疎通を図って、両者合意・納得の上で治療を受ければ良い。
記事を読み進める前に…
私は精神科や心療内科に通院している人の中に、主治医とのやり取りで苦労する人の存在を聴いたことがある。例えば次のように思う人がいるようである。
そうでなくても、
もいるかもしれない。
そこで当記事では、私が主治医の診察時に、
- どのように自分の心身の状況や困っていることについて伝えているか
- 主治医からの助言をどのように聞いているか
を可能な範囲で読者の皆様に共有したいと思う。
それと私の経験を踏まえて、「精神科医・心療内科医との適切なコミュニケーションの取り方」について、私の持論を書こうと思う。
読者のみなさまにはもし気が向けばこの記事を一読していただき、賛成・反対のどちらの立場でも構わないので、率直な意見をコメントなどに残していただけると幸いである。
なお私は月に1回程度かかりつけの心療内科に通院している。そこで5~10分程度の診察時間に主治医とやり取りしている。
私は今の主治医とは十分に意思疎通が取れていると思っている。また少なくともうつ病に関しては、多少の症状の変動があっても安定した状態が長期間続いている。
ついでに「+α」として、心理職員や福祉職員についても少し触れた。本論からは脱線してしまうが、場合によっては主治医以外に心理職員・福祉職員も力になり得るからである。
リンク





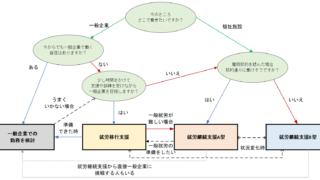




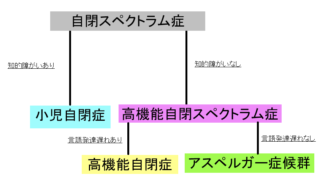

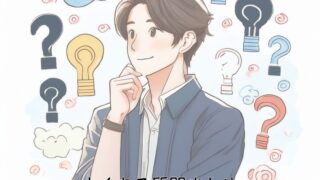









コメント