当記事のまとめ
「ピア精神保健福祉士」の定義を箇条書きにすると…
以上をまとめると、私個人は「ピア精神保健福祉士」について、少なくとも以下の事項をすべて満たしている人のことをいうと思う。
- 精神保健福祉士(MHSW・PSW)の国家資格を取得している。
- 「障害者ピアサポート研修」やそれに準ずる研修・講座を受講するなどして、ピアサポートについてよく理解している。
- 「精神保健福祉士としての関わり方」「ピアサポーターとしての関わり方」双方を十分理解し区別できる。
- 支援を行う相手に応じて「精神保健福祉士としての関わり方」「ピアサポーターとしての関わり方」をうまく使い分けられる。
ただ単に「精神保健福祉士」(MHSW・PSW)の資格を持ち、ピアサポートの知識があるだけでは、「精神保健福祉士兼ピアサポーター」にはなれても、本当の意味での「ピア精神保健福祉士」にはなれないのではないかと私は考えている。
もちろん上記以外にも「ピア精神保健福祉士」の定義に当てはまりそうな事項があるかもしれない。もしくは私の考えるこの定義に異論を述べる人もいるかもしれない。もし何かご意見があれば、コメントなどで教えていただけるとありがたい。
この定義から私自身は「ピア精神保健福祉士」と堂々と名乗れるのか
ちなみに私はこの私見に基づき、自らが「ピア精神保健福祉士」と堂々と名乗れるのかどうかを考えた。結論からいうと、「ピア精神保健福祉士」と名乗れるようになるためにはもっと経験と知識が必要だろうと思う。
2025年5月まで私はパートで就労移行支援の職員として働いていたが、利用者に対しては「専門職的な関わり」の方が圧倒的に多かったと感じている。逆に支援の際に「ピアサポーターのような関わり方」をした機会は今のところ少ない。
今後私が「ピア精神保健福祉士」に近づくためには、実際の支援の現場で試行錯誤しながら、「専門職的な関わり」「ピアサポーターとしての関わり」双方を実際に使い分けられるようになることが必要だと自分自身で考えている。
当記事の参考文献
- “e-Gov法令検索”「精神保健福祉士法(令和6年5月27日施行)」(2025年2月25日アクセス)
https://laws.e-gov.go.jp/data/Act/409AC0000000131/598392_1/409AC0000000131_20240527_503AC0000000037_h1.pdf - 厚生労働省(発行年不明)「精神保健福祉士について」(2025年2月25日アクセス)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/seisinhoken/index.html - 社会福祉法人豊芯会(2022)「基礎研修テキスト(改訂版 vol.1)」(2024年7月9日アクセス)
https://housinkai.or.jp/Portals/0/PDF/Notice/%E2%98%85%E2%98%850331_2022_%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88_%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88vol.1-%E5%9C%A7%E7%B8%AE.pdf - 日本精神保健福祉士協会(発行年不明)「精神保健福祉士について」(2025年2月25日アクセス)
https://www.jamhsw.or.jp/mhsw/index.html

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の概要と当ブログ筆者の思い出
社会福祉士および精神保健福祉士の国家試験の概要と、私が受験した時の思い出について。

【障害者福祉】私が福祉の仕事をして良かったと思うこと【福祉施設・作業所】
私自身が福祉施設(障害者のB型作業所・就労継続支援B型)に勤めて良かったことのまとめ。また、福祉の仕事を経験して良かったこと。

就労継続支援B型事業所とは?利用者・仕事内容・役割・メリットについて【元職員が解説】
就労継続支援B型事業所(B型作業所)の仕組みや仕事内容、メリット・役割・利用者像を、元職員の経験を交えて解説する。

精神保健福祉士の精神疾患当事者が「クローズアップ現代」(2月12日放送分)を見て【心の病・精神障害】
心の病(精神疾患・精神障害)について取り上げたNHKの「クローズアップ現代」(2025年2月12日放送分)を見た感想と、心の病当事者として今後の要望

テーマ別ブログ記事まとめ
福祉やメンタルヘルスに関する制度・サービスをテーマ別に整理。「福祉ウォッチャーT」の記事から、知りたい情報にすぐたどり着けます。
リンク


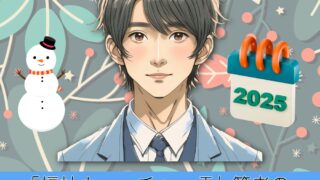
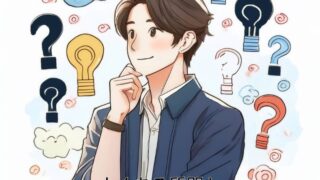







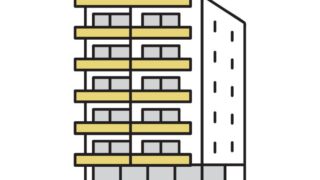

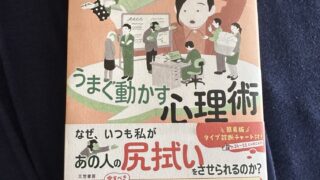



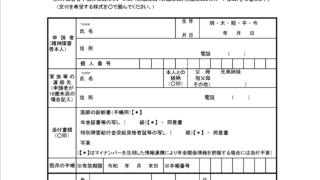

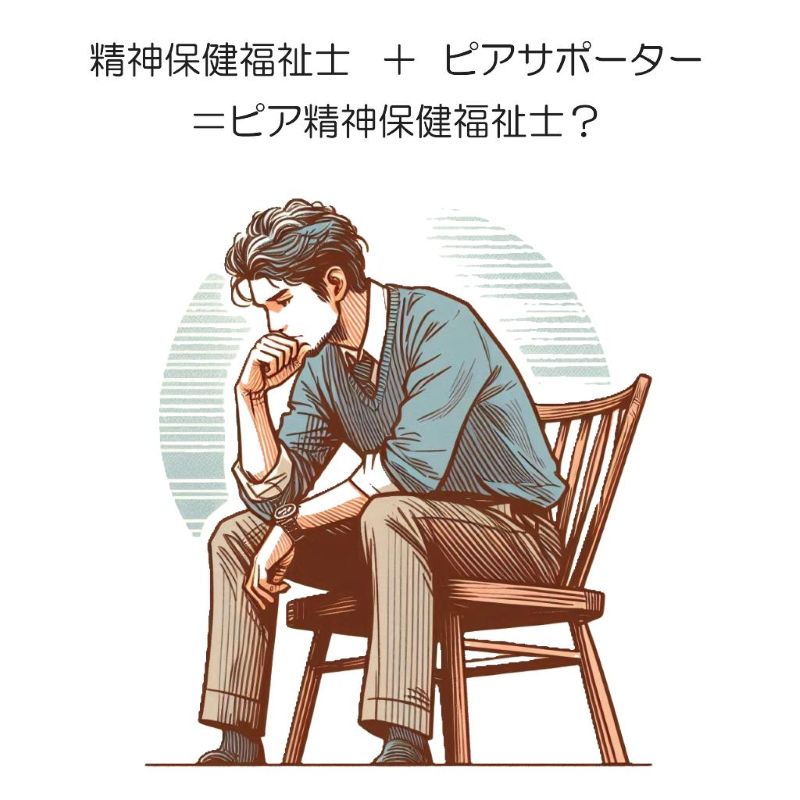

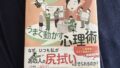
コメント