心身の状況・困りごとの伝え方
私の場合はどうしているか
私が普段かかりつけの心療内科の主治医と会話する際には、短い時間でも自らの伝えたいことを上手く伝えられるように、事前にある程度話したいことをまとめている。
過去には事前に少し時間を取って要点をまとめた紙を主治医に渡す時期もあった。現在は診察前の待ち時間を使い、頭の中で2~3つほど言いたいことを考えている。
実際の診察では、たいてい以下のことを伝えている。最後に薬の処方を主治医と私で確認して、診察終了である。
- 自分の心身の状況について:「睡眠リズム」や「強いストレスを感じたこと」など
- 近況報告:良かったことも悪かったことも
- (ときどき)特に変わったこと
私の場合はこのようにして、長くて10分程度の診察時間に収めている。私はこの方法で、主治医に必要なことをおおむね伝えられている。
もし私がアドバイスできるとすれば…
精神科や心療内科での診察時間は、初診ならともかく再診になると「長くても10分」という印象を私は持っている。
多くの医師は可能な限り丁寧に患者を診察しようとしているが、他の多くの患者も診察しなければならない。そうなると、1人に掛けられる診察時間にどうしても制約が出てしまう。
もちろん「診察時間が5分未満」とか「大半が薬の処方に関する話」ということはさすがに極端だと思う。
それでも例えば
状態が比較的安定している患者の診察時間を少し短くして、心身の状況が良くない患者に対しては少しでも長く診察時間を取ろう
という医師の考えなら私は理解できる。
そもそもあまり長くない診察時間でも効率良く診察を進めるのは医師の仕事である。しかしもし私が普段行うように、事前に言いたいことを2~3点にでもまとめておけば、患者にとっては
という経験が減るのではないか。
頭の中でうまくまとめられない場合は、紙に書いてまとめても良い。「伝えたいことの題名」だけを2~3点書くだけなら、メモ用紙1枚でも十分過ぎる。
このメモ用紙を主治医に渡せば、多くの場合それに沿って主治医が診察を進めるはずである。それと患者側にとっては「伝えたいことを伝え忘れる」失敗が減る効果もありそうである。または手元にスマートフォンがあれば、それにインストールされているメモアプリを使う手もある。
いずれにしても、主治医に伝えたいことを伝える方法を身につけられれば、患者側の心理的メリットは大きいと私は考える。思いを主治医に表現できずストレスを抱えるよりははるかに良いはずである。
主治医以外の職員や外部機関の活用
若干話が脱線してしまうが、ときには「困りごとが多くて10分では到底伝えきれなかった」という経験を持つ人も多いと思われる。もちろん病気・障害に関わる話や薬に関する話など、主治医に相談しないと解決できない話がある。
しかし医師以外にカウンセリングに精通している公認心理師・臨床心理士といった心理職員や、福祉制度やサービスに詳しい精神保健福祉士などの福祉職員がかかりつけの病院・診療所にいる場合がある。
もし心理職員や福祉職員がかかりつけの医療機関にいれば、この人達にも困りごとを相談できる可能性がある。
それとかかりつけの医療機関にこの人達がいない場合でも、医療機関の窓口に相談すれば、お住まいの市町村にある保健所や福祉施設などを案内してもらえることがある。
または病院や診療所内に置いてあるパンフレットやポスターがあれば確認して欲しい。ときに地域の保健所や福祉施設等の連絡先が掲載されている。
保健所や福祉施設には心理職員や福祉職員が配置されている。保健所や福祉施設はかかりつけの医療機関と連携して対応するはずである。
心理職員や福祉職員の役割
例えば困りごとが「話を聴いて欲しい。話をできれば気持ちが楽になりそう」という内容であれば、心理職員のカウンセリングが効果を発揮するかもしれない。カウンセリングでは主治医の診察より長時間話ができる場合が多い。1回あたりの時間として多いのは30分や60分だろう。
もちろんカウンセリングの利用に関しては、あらかじめ主治医に相談する必要がある。または主治医からカウンセリングの利用を提案されることもあるだろう。カウンセリングにかかる費用は事前に確認して欲しい。
それと障害年金の受給や精神障害者保健福祉手帳の申請など、福祉制度・サービスに関する相談は福祉職員が主に対応する。例えば診断書の作成は医師でないとできないが、制度・サービスの説明や患者が記入する書類の記入支援などは福祉職員が得意とする。
また金銭の問題や住まいの問題など、患者の生活に関わる相談を福祉職員にすることもできる。この場合福祉職員は利用可能な公的制度・サービスの案内や、他の公的機関・福祉施設などにつなぐこともある。
心理職員や福祉職員への相談の中には、主治医に相談すべき医療に関係する内容が含まれることもある。その場合は患者の了解を得て、心理職員・福祉職員から主治医に相談内容が共有されるはずである。

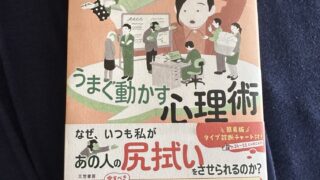



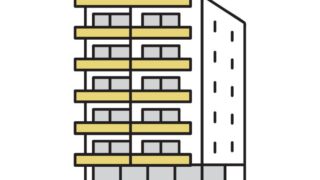
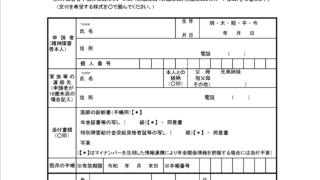








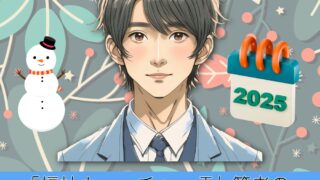
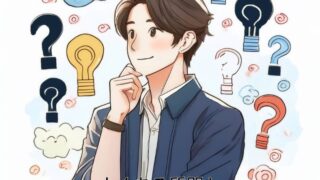





コメント